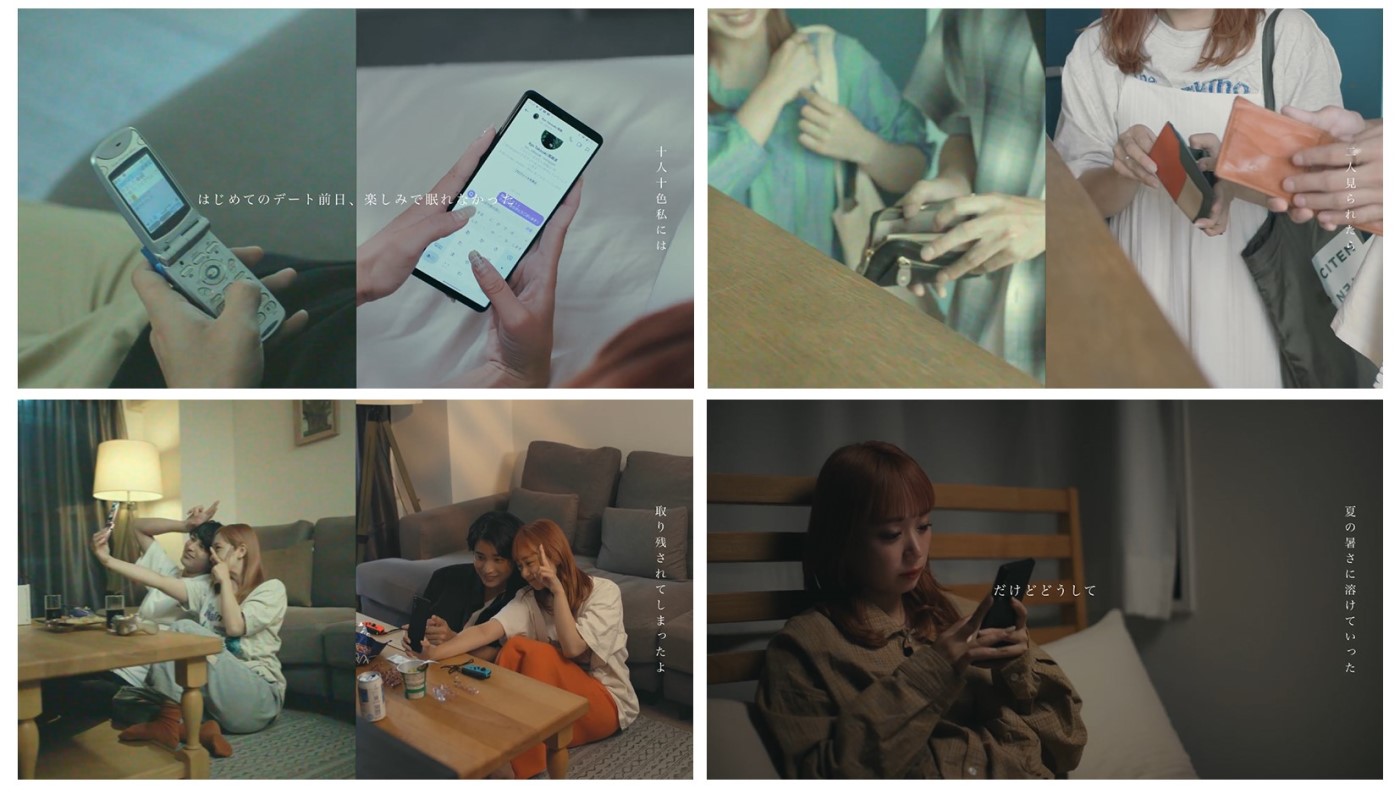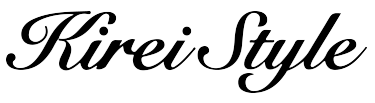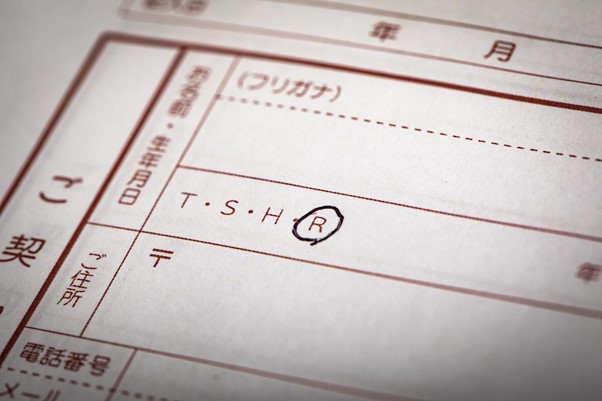
万葉集ってなんだっけ!

小学校だったか、中学校だったか…日本人ならば1度は耳にしたことがあるはずの『万葉集』。なんだか暗記した様な記憶があるけど、どんな本だっけ…と思っている方、いませんか?私はすっかり忘れてしまっていました。折角なので、思い出してみましょう。
日本の誇り、万葉集
万葉集は日本最古の歌集です。奈良時代ごろ、現在日本に残されているものの形に整ったそうです。万葉集は歌集ですので、もちろんいくつかの歌で構成されています。その数なんと4,500首。仁徳天皇の時代(5世紀はじめ)〜淳仁天皇の時代まで、約350年の間に詠まれた詩達なのだそうです。
1300年も前に、皇族や貴族だけでなく一般市民である農民や遊女の歌が収められたのです。これは日本が誇る特徴だそうで、ここから元号を決めただなんてなんだかかっこいいと思いませんか?
梅花の歌
新元号「令和」が万葉集から引用されたという話はなんとなく知っていても、『梅花の歌』から引用されたということはあまり知らないのではないでしょうか。この『梅花の歌』は、万葉集の5巻に収められています。
作者には諸説ありますが、”大伴旅人”だと言われているそうです。この中で用いられている”令月”というおめでたい月を表す言葉から「令」を、”気淑風和”という風の心地よさを表す言葉から「和」を取り、「令和」という元号が完成したのです。
「日本の四季折々の文化と自然を、これからの世代にも引き継いでいきたい」という安倍首相の思いから万葉集の『梅花の歌』より引用することを考えたそうですよ。趣があって素敵ですね。
大伴旅人という人物
万葉集には柿本人麻呂、額田王、天智天皇、持統天皇などなど…どれも古典で覚えたなあと思い出せるような、そうそうたるメンバーの詩が収められています。これらの人々の詩はもちろんですが、今回令和の引用元となった『梅花の歌』を書いた大伴旅人、気になりますよね。
大伴旅人は665年生まれ、67歳で他界、と当時からすると長生きな方だったようです。父の大友安万侶も歌人で、彼の歌も万葉集に収録されています。大伴旅人は政治家としても名を残しましたが、武将としても有名だったそうで、その多才ぶりが伺えますね。
また、同じ大伴と同じ姓を持つ大伴家持ですが、彼は万葉集の編纂に関わっています。なんだか万葉集とつながりの多そうな大伴という姓ですが、なんと大伴家持と大伴旅人は実の親子なんだそうです。大伴家は3代に渡り万葉集に深く関わっているという事ですね。恐れ入りました…
知っておきたい日本の古典
万葉集について詳しく触れてきましたが、日本の古典って万葉集以外にも沢山ありますよね。この機会に他の日本古典についても少し知ってみませんか。
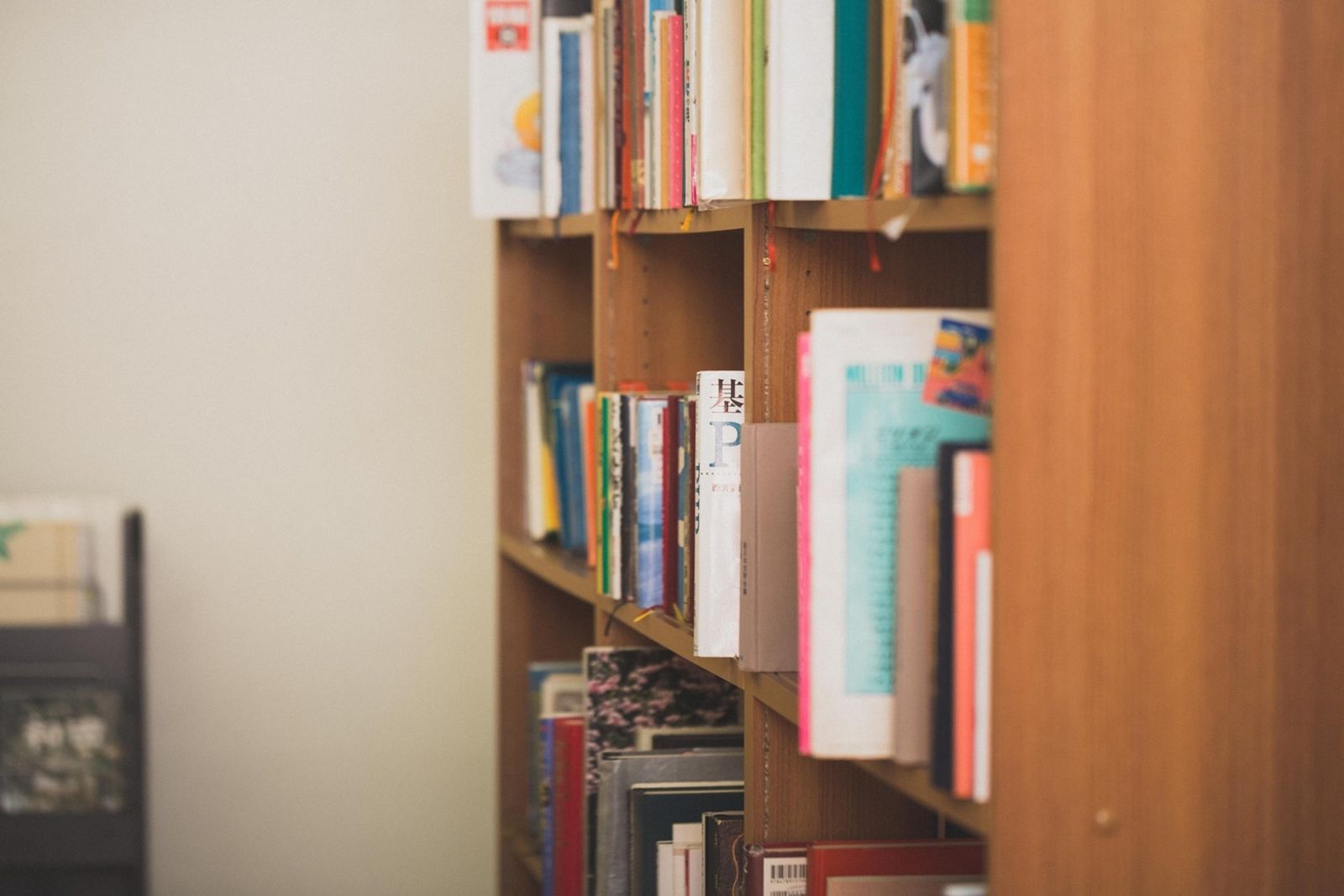
古事記
古事記は、天武天皇の命令により奈良時代にまとめられた、日本最古の典籍です。日本最古の歌集、万葉集より昔に遡ります。古事記は「上つ巻」、「中つ巻」、「下つ巻」の3つの巻から成り立っており、作者としては稗田阿礼や太安万侶らが関わっています。
出雲神話が中心となり、「因幡のしろうさぎ」が有名なエピソードとして挙げられますね。文体ですが、「ひらがな」や「カタカナ」がまだ使われておらず、漢字で書かれており、物語調になっています。
内容は主に神話時代の話で成り立っていて、「上つ巻」は1巻まるまる神話が書かれており、天地が分かれ日本列島ができた事から「誰が、何をしたのか」という観点で天皇家の歴史までもが示されています。日本文化の原点とも言えますね。
日本書紀
古事記と同じく天武天皇の命令により記された日本書紀。全30巻と、古事記の10倍もの巻数があります。舎人親王などが中心として関わっており、神話のエピソードはあまり書かれておらず、30巻のうち、最初の1、2巻のみで記されています。
本文は漢文で書かれており、出来事を年代順に記載する編年体をとっています。つまり「いつ、何が起こったのか」という形ですね。国家の公式な歴史が書かれており、古事記とは似ているようで違った形の古典であることがわかりますね。
風土記
奈良時代のはじめ、当時の天皇の元明天皇が各国の役所にその国内の地名・土地の産物・土地の状態・地名の起源・土地に伝わる伝承をそれぞれ提出させました。それをまとめたものが、風土記となります。
つまり土地の状況や伝承をまとめたもの、という事です。
様々な国から集めて完成した風土記ですが、現在完全な状態で残っているものは出雲国風土記しかありません。他に播磨国・常陸国・豊後国・肥前国のものが1部のみ残っているそうです。
まとめ
なんだか久しぶりにしっかり勉強したような気持ちになりましたね。学生の頃、ただただ暗記するだけだった古典文学も、新元号、令和のおかげでとても近しいもののように思えてきたのではないでしょうか?
大伴旅人も、まさか自分が書いた歌から元号が作られるだなんて夢にも思っていなかったことでしょう。果てしない時を超えて令和という元号は人々の元にやってきたわけです。少しでも古典を知っていると令和により愛着が湧いてくるのはずです。せっかく詳しくなった元号や万葉集の歴史、友達や家族に話してみては?
参考url
・ニッポン放送
http://www.1242.com/lf/articles/168343/?cat=politics_economy&pg=cozy
・ヤドカリコ.com
・THE SANKEI NEWS
https://www.sankei.com/life/news/190408/lif1904080016-n3.html
・LIG
・nhk政治マガジン
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/16043.html
・グノシー
https://gunosy.com/articles/ag4FK
・japanknowledge
https://japanknowledge.com/contents/koten/title.html
・なら記紀・万葉
http://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/manabu/chigai/
・歴史をわかりやすく解説!ヒストリーランド
-

- 1
- 2