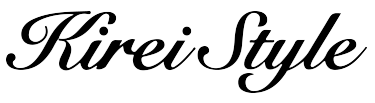「雨が続くと咳がひどくなる…」
「台風が近づくと呼吸が苦しい…」
など、
もしかしたらそれは喘息かもしれません。
気温や湿度、気圧の変化が激しいこの季節は、喘息の発作が多くなる傾向にあります。
湿度が高くなると、カビも増えやすく、ますます喘息の悪化の原因に…。
本記事では、喘息と気管支炎の違いやおすすめの対策について解説していきたいと思います。
喘息(ぜんそく)とは

喘息とは、気道(空気の通り道)に炎症が起き、さまざまな刺激に対して気道が敏感になり、発作的に気道が狭くなることを繰り返す病気です。
1.症状
喘息の特徴的な症状を解説していきたいと思います。
<喘息の症状の特徴>
咳が続き、息苦しくなる
呼吸のたびにゼーゼー、ヒューヒューという音がする
<症状が出やすい状況>
夜間から早朝
運動中や冷気にあたるなどの刺激があったとき
台風の接近や季節の変わり目
症状がない状態でも、少しの刺激で咳が出やすいのが特徴です。
2.原因
喘息は、多様な原因が複雑にからみあって発症すると言われています。
<喘息発作に関わりが深い要因>
ペットの毛
ダニ、カビ、ホコリ
タバコの煙
急激な気温の変化
ストレス、疲労
大人になってから喘息を発症した場合、その要因が子供に比べて多いことから、完治は難しいと言われています。
喘息と気管支炎の違いとは

喘息も気管支炎も、どちらもおもな症状は咳。
喘息は、慢性的に続く気道の炎症が原因の咳で、毎日炎症の治療が必要です。
一方で気管支炎は、風邪やインフルエンザなどが原因の気道の炎症による咳です。
対症療法や自然治癒で改善が期待できます。
気管支炎については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。
喘息の症状におすすめ対策3選

こちらの章では、喘息の咳におすすめの対策を解説していきたいと思います。
1.ダニ・カビ・ホコリなどのアレルゲンを避ける
日常生活で、アレルゲンを避けることを意識してみましょう。
掃除機は毎日かける
布団は日光にあてて、掃除機で布団のホコリを吸い取る
エアコンの内部はこまめに掃除をする
毛のあるペットはなるべく室内に入れない
生活のなかで、いつ症状が悪化したのかを振り返り、自分に合った対策を見つけられるといいでしょう。
2.湿度を保つ
湿度が高すぎると、カビが発生するおそれがあります。
特に、梅雨の時期は部屋の湿度が高くなりやすく、カビ発生の危険も高まります。
除湿器などを利用して、湿度が30~50%になるようにしましょう。
3.医療機関の受診
さまざまな対策をしても、咳や息苦しさが続くときは、医療機関を受診しましょう。
喘息の薬には、内服薬・吸入薬・貼付薬などがあります。
吸入薬は、正しい使用方法を守ることが大切です。
使用する際は、医師や薬剤師に使用方法を指導してもらいましょう。
喘息の症状には漢方薬もおすすめ

喘息の発作や症状の悪化を防ぐには、漢方薬も役立ちます。
喘息対策には、
「気管支を広げて呼吸をしやすくする」
「酸素や栄養を肺に届け、呼吸器の機能を回復する」
「気道の炎症をやわらげる」
「痰(たん)を出しやすくする」
といった作用がある漢方薬を選び、根本改善を目指しましょう。
<喘息対策におすすめの漢方薬>
●麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
気管支を広げる作用があり、咳や痰、のどの渇きを抑え、呼吸を楽にします。
喘息発作のような激しい咳に用いられます。
●柴朴湯(さいぼくとう)
自律神経を安定させるとともに、のどや肺・気管支の炎症をやわらげ、痰をとり去ります。
咳や喘息だけでなく、神経症にも効果が期待できます。
自分に合う漢方薬を知りたいという人には、漢方の専門家にオンラインで個別相談ができる『あんしん漢方』などのサービスもおすすめです。
AI(人工知能)が個々人に効く漢方を見極めて、自宅まで郵送してくれるという手軽で便利なサービスです。
まとめ
これから迎える梅雨などの雨の多い時期は、喘息持ちの方にとっては特にツラい季節…。
喘息は、放置しておくと重症化してしまうケースもあるため、しっかりと対策するようにしましょう。
こまめな掃除や湿度の管理などに加え、漢方薬もうまく活用するなどして、症状の悪化を防ぐことが大切です。
執筆者プロフィール

あんしん漢方薬剤師
山形 ゆかり
薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。
病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角や吉野家など15社以上の飲食店の薬膳メニューの開発にも携わる。
また、前章でご紹介したオンライン漢方提供サービス『あんしん漢方』でも薬剤師としてサポートを行っている。