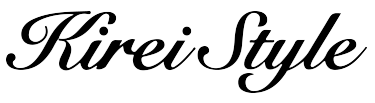お正月と言えば、「初詣(はつもうで)」。
新年を迎え、神様や仏様に「今年もよろしくお願いします。」とご挨拶をすることで、心機一転がんばろう!という新鮮な気持ちになりますよね。
そんな初詣ですが、ご存知の通り、「神社」と「お寺」でお参りの仕方が異なります。
そんな初詣の作法ですが、しっかりマスターできている方は、意外と少ないのではないでしょうか?
「あれ、柏手を打つのは神社?お寺?」
「お手水(おちょうず)ってどうやって使うんだっけ?」
そんな風に戸惑っている方も多いはず。
そこで今回は、初詣で恥をかかないための、「お参りの正しい方法」をご紹介したいと思います。
INDEX
初詣っていつから始まったの?
初詣のマナーについてお話する前に、まずは初詣の由来についてお話ししておきたいと思います。予備知識を知っておくだけで、いつもの初詣がぐんと面白くなりますよ。
初詣というとはるか昔から行われてたイメージがありますが、実は現代の初詣スタイルになったのはつい最近のこと。
江戸時代は、大晦日の夜から元旦にかけ、一家の家長が地域の神社に泊まり、豊作などをお祈りするという「年籠り(としごもり)」スタイルが主流でした。
そもそも、当時は電車もバスも自動車もありませんでした。
そのため、現代のような初詣は事実上不可能だったのです。
昔は、元旦は初詣をせずに家で過ごすというのが一般的でした。
しかし、明治時代に入り文明開化が進み、鉄道などの交通機関が生まれたことで、遠く離れた神社やお寺へお参りすることが可能となりました。
それにより、徐々に3が日の初詣が人々に普及していったのです。
初詣の意味って?
そんな初詣ですが、そもそも初詣ってなんのために行うのでしょうか?
簡単に言ってしまうと、神様や仏様への「ご挨拶」です。
新しい年に切り替わった節目に、昨年の感謝と、今年の願いを伝えにいく機会なのです。
つまり、
「昨年は一年間見守っていただいてありがとうございました。」
「そして、今年もどうぞよろしくお願い致します。」
というご挨拶を、神様・仏様に伝えにいくのが「初詣」です。
初詣のマナーって難しい?
そんな初詣ですが、「マナーが良く分からない・・・」と苦手意識を持っている方も少なくないのでは?
初詣は神様にご挨拶にいく神聖な宗教儀式ですし、周りに大勢の人がいるということもあって、マナーを間違えてしまうのは極力避けたいですよね。
もちろん、一番大事なのは「神様や仏様に対する気持ち」ですが、やはり最低限のマナーは押さえておきたいもの。
一番気を付けたいのが「神社のお参りのマナー」と「お寺のお参りのマナー」をごっちゃにしてしまうこと。
同じお参りとは言っても、神社とお寺では作法が異なります。
神社にお参りするときに、お寺の作法でお参りしてしまったり、お寺にお参りするときに、神社の作法でお参りしてしまうのは、とても恥ずかしいもの。
ここからは、初詣で恥をかかないための「初詣の参拝方法(神社編)」と「初詣の参拝方法(お寺編)」をそれぞれご紹介していきたいと思います。
初詣の参拝方法(神社編)

まずは、神社でのお参りの方法からご紹介します。
(1)鳥居の前で1回おじぎをする
神社の門である「鳥居」は、人間が住む世界と神様が住む世界の境界線(結界)であると考えています。
そのため、まず鳥居の前に来たら、「神様のお宅におじゃまします。」という気持ちで、1回おじぎをします。
(2)手水(ちょうず)で手と口を清める
参道を進んでいくと、「手水舎(ちょうずや)」が見えてきます。
神様に会う前に、ここでしっかりと身を清めておきましょう。
1、まず、ひしゃくを右手に持って、左手にかけます。
(ひしゃくを左手に持ち替えて右手もおなじように清めます。)
2、ひしゃくを右手に持って、左手の手のひらに水を溜めます。
その水を少し口に含んで、口をすすぎます。
※水を口に含むのに抵抗がある場合は、ほんの少し唇を湿らせるだけでも大丈夫です。
3、唇がふれた左手は、もういちど水をかけて清めます。
4、ひしゃくを手前に傾けて縦にします。
(つたって流れ落ちてくる水で柄を清めます。)
5、ひしゃくをもとの場所に戻して、おしまいです。
水を右手にかけたり、左手にかけたりと動作がややこしいように感じますが、
最初にひしゃくを左手に持ち替えるとき以外は、「終始右手にひしゃくを持っている」というポイントを覚えておくと分かりやすいかもしれません。
「手を清める」→「口を清める」→「柄を清める」という順番さえ覚えておけば間違えることはないでしょう。
(3)賽銭箱の前で軽く会釈する
ご神前まで来て賽銭箱の前に立ったら、まず軽く会釈をします。
(4)賽銭箱にお賽銭を入れ、鈴をならす
賽銭箱に静かにお賽銭を入れます。
鈴があったら、鈴を鳴らします。
(5)2回おじぎ & 2回拍手をする
2回深くおじぎをしたら、胸の前でパン、パンと2回拍手をします。
(6)両手を合わせて祈る
心を込めて、昨年の感謝や今年の挨拶をお祈りします。
(7)1回おじぎをする
お祈りが終わったら、最後に深く1回おじぎをします。
(8)鳥居の前で1回おじぎをする
帰る際は、鳥居の前で1回おじぎをします。
初詣の参拝方法(お寺編)

続いて、お寺でのお参りの方法をご紹介したいと思います。
(1)山門の前で1回おじぎをする
神社の場合と同じく、お寺の門である「山門」は、俗世との境界線だと言われています。
そのため、山門の前で1回おじぎをします。
(2)手水(ちょうず)で手と口を清める
お寺にお参りする時も、手水(ちょうず)で手と口を清めます。
やり方は神社の場合と同じです。
(3)常香炉(じょうこうろ)で煙を浴びる
境内に常香炉(じょうこうろ)があったら、煙を浴びます。
常香炉の煙を浴びることには「体を清める」という意味があります。
(4)賽銭箱の前で1回おじぎをする
本堂まで来たら、賽銭箱の前で1回おじぎをします。
(5)賽銭箱にお賽銭を入れ、鈴をならす
お賽銭を静かに入れ、
鈴があったら鳴らします。
(6)両手を合わせて祈る
心を込めて、昨年の感謝や今年の挨拶をお祈りします。
※拍手はしません。
(7)1回おじぎをする
お祈りが終わったら、最後に深く1回おじぎをします。
(8)山門の前で1回おじぎをする
帰る際は、鳥居の前で1回おじぎをします。
神社とお寺の参拝方法を整理!
さて、このように、意外とお参りにはプロセスが多いことが分かりますね。
少しややこしいので、整理したいと思います。
神社の参拝方法
鳥居の前でおじぎ
↓
手水で手と口を清める(左手、右手、口、ひしゃくの柄、の順)
↓
賽銭箱の前で会釈
↓
お賽銭を入れて鈴を鳴らす
↓
2回おじぎ&2回拍手
↓
祈る
↓
1回おじぎ
↓
鳥居の前で1回おじぎ
お寺の参拝方法
山門の前でおじぎ
↓
手水で手と口を清める(左手、右手、口、ひしゃくの柄、の順)
↓
常香炉(じょうこうろ)で煙を浴びる
↓
賽銭箱の前で一礼
↓
お賽銭を入れて鈴を鳴らす
↓
祈る
↓
1回おじぎ
↓
山門の前で1回おじぎ
上の赤文字の部分が、神社とお寺の参拝方法において違う点です。
神社の場合はお祈りする前に「2回おじぎ、2回拍手」をしますが、お寺の場合はしません。
よく間違えやすいので、気を付けるようにしましょう。
参拝する時の注意点
以上が基本的な参拝方法になりますが、参拝する時の注意点が2つあります。
(1)神社では、参道の中心を歩かない
神社の場合、参道の真ん中は神様の通り道だと言われているので、できるだけ避けて通るのがベターです。
しかし、初詣の時は混雑していてそうも行かない可能性も高いので、臨機応変に対応しましょう。
お寺の場合は真ん中を通っても大丈夫です。
(2)お寺では、敷居をまたぐ
お寺の山門には「敷居」がありますが、これは踏まずにまたぐようにしましょう。
「建物が傷んでしまうのを防ぐため」「俗世との結界を踏むのは失礼に当たるから」などの説があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本日は、「初詣のマナー」をご紹介しました。
毎年1回行っているはずの初詣ですが、意外とそのお参り方法はわすれてしまいがち。
大人なら必要最低限の作法は覚えておかないと恥をかいてしまうかもしれません。
初詣まえに今一度予習をして、パーフェクトな初詣をめざしましょう♪
<参考URL>
・タウンワークマガジン https://townwork.net/magazine/skill/58614/