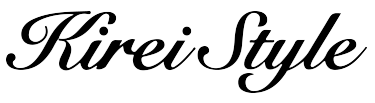おせちを安く手作りしたい!おしゃれで簡単なレシピなどをご紹介

お正月に家族でゆっくりと三が日を過ごすときには、おせちがあると華やかですよね。しかし伊達巻や紅白のかまぼこ、栗きんとんや伊勢海老、黒豆などが入っているおせちは、味が良いだけでなく見た目も豪華なだけに、購入するとなると高くついてしまいます。
今回は、そんなに贅沢はできないけれど、おせちは食べたいという方に向けて低予算で簡単に作れるおせちのレシピや作り方のコツをご紹介します。
おせちとは
おせち(御節)とは、季節の節目である「節」の日を指す言葉です。おせちのはじまりは、平安時代の朝廷がお正月を含んだ年に5回ある「節」の日(節句)に、神に供える料理として「御節供(おせちく)」を提供していたことだといわれています。
その後、時代の流れとともに庶民の食卓にも浸透し始め、やがておせちは最も大切な正月の料理として認知され、作られるようになりました。
おせちを作るのは何のため?
さて、毎年お正月ではなく年末におせちを作るのはどうしてでしょうか。その理由は、日本では年が明けてからの三が日は台所を使わないという風習が存在するためです。これは三が日は接待で忙しいことや、包丁は「縁を切る」ことを連想させるため使わないといった言い伝えが関係しています。
そのため、おせち料理には3日間台所に立たなくていいだけの量が入っていたり、煮物のような保存食といわれるある程度長期保存しやすいお料理が入っていたりするのです。
一般的なおせちの中身は?
平安時代のおせちは豆腐やこんにゃく、季節の野菜や昆布を使用した料理がメインでした。一方で現代のおせちはバラエティに富んでいるといえます。伝統的な和食だけでなく、洋食のおかずが入っていたり中華風のオードブルだったりと、さまざまな種類のおせちがあるのです。
- 1
- 2
-

1/2 ページ