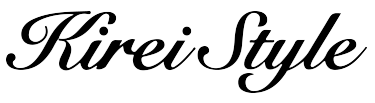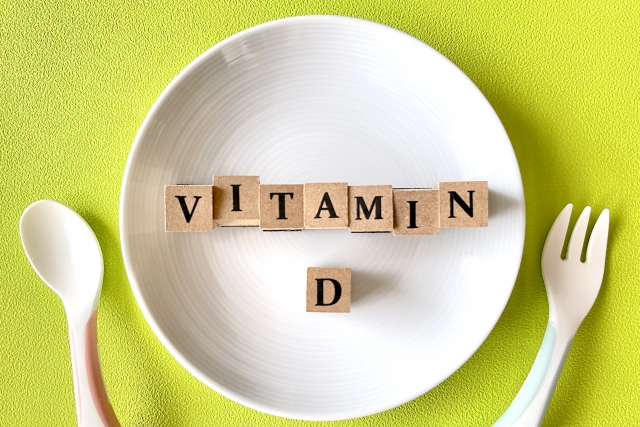
近年、新型コロナウイルスをはじめとするさまざまな感染症の流行に伴い、免疫の重要性が再認識されています。
そのうえで注目を集めているのが「免疫のビタミン」と呼ばれる、ビタミンD。
免疫を正常な状態に保つために欠かせないビタミンです。
しかしその一方、現代人は深刻なビタミンD不足に陥っており、「98%の日本人がビタミンD不足に該当する」という説も。
そこで本日は、そんなビタミンDにフォーカス。
「ビタミンDとはどんなビタミンなのか」
「欠乏するとどうなる?逆に過剰症は?」
「不足しがちなビタミンDを充足させる方法は?」
といった疑問に答えていきたいと思います。
現代人の98%はビタミンDが不足している

ここ最近その名を聞くことが多い、ビタミンD。
新型コロナウイルスが流行したころから、ビタミンDの重要性が叫ばれるようになってきましたよね。
ビタミンDは、鮭やきくらげなどに含まれる脂溶性ビタミンの一種で、「免疫のビタミン」と呼ばれるほど免疫力の維持に欠かすことのできない栄養素です。
食事から摂取するほか、紫外線を浴びることで皮膚でも作られるという少し変わった特性があります。
そんなビタミンDですが、実は多くの方が深刻なビタミンD不足に陥っているということで問題視されています。
東京慈恵会医科大学が5,518人の男女を対象に行った調査によると、なんと98%がビタミンD不足に該当していたということが明らかになったのです。
(参考:https://www.jikei.ac.jp/news/pdf/press_release_20230605.pdf)
ちょっと驚きですよね。
でも、なぜここまで多くの人がビタミンD不足に陥っているのでしょうか?
ビタミンD不足の理由(1)ビタミンDを含む食品が少ない
その理由のひとつとして挙げられるのが「ビタミンDを豊富に含む食品が少ない」ということ。
ビタミンDは魚類やきのこなどには含まれている一方、野菜類・果物類・穀類などにはほとんど含まれていません。
肉類には多少のビタミンDが含まれていますが、魚類やきのこ類と比較すると微量です。
普通の食生活だけではそもそも不足してしまう傾向がある上、近年は若者を中心に「魚離れ」が進んでいることもビタミンD不足に拍車をかけていると考えられます。
ビタミンD不足の理由(2)日光を浴びる時間が少ない
またもうひとつの理由として挙げられるのが「日光を浴びる時間が少ない」ということ。
前述の通り、ビタミンDは紫外線を浴びることで、皮膚で合成されるという特徴があります。
しかし、近年はデスクワーク中心の社会となっており、外に出る機会が減ってきているため、ビタミンDの合成量が減少していると言われています。
特に女性の場合、美容のために紫外線対策を行っている方も多いですよね。
日焼け止めを塗ってしまうと紫外線が肌に届かなくなってしまうため、ほとんど皮膚でビタミンDが合成できなくなってしまうのです。
ビタミンDに期待されている効果

このように、多くの方が不足状態に陥っているビタミンD。
では、しっかりとビタミンDを摂取すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここからは、ビタミンDを充足させることにより期待できる効果をご紹介したいと思います。
免疫力を整える
先ほどからお伝えしている通り、ビタミンDは免疫力に欠かすことのできないビタミン。
しっかりと充足させることにより、免疫力が整うという効果が期待できます。
私たちの身体の中には、体内に侵入してきた細菌やウイルスをパクパクと食べて死滅させてくれる「マクロファージ」という免疫細胞がいます。
ビタミンDにはこのマクロファージを元気にさせるはたらきがあるため、さまざまな病気や感染症にもかかりづらくなり、免疫力の向上が期待できるのです。
ですが、ビタミンDはただ免疫力を向上させてくれるだけではありません。
「過剰な免疫反応は抑えてくれる」という特徴もあるのです。
私たちの体内に細菌やウイルスが侵入すると、炎症性サイトカインという物質が分泌されます。
炎症性サイトカインは病原体をやっつける上で必要なものですが、これが過剰に分泌されてしまうと、正常な細胞までダメージを受けてしまう「サイトカインストーム」が起こってしまいます。
サイトカインストームが起こってしまうと、最悪の場合、死に至ることもあります。
しかし、ビタミンDにはこの過剰な炎症性サイトカインを抑えてくれる働きがあるため、不要な炎症やサイトカインストームを抑える効果が期待できるのです。
このように、ビタミンDには免疫力を「強すぎず、弱すぎず、ちょうど良い状態」に整えてくれるという、調整係としての役割があります。
骨を強くする
ビタミンDには「骨を強くする」というはたらきもあります。
よく、牛乳などの乳製品に「ビタミンD入り」という文言が書いているのをみたことはありませんか?
これは、ビタミンDに「カルシウムの吸収を高める」という特性があるため。
カルシウムというのは実は吸収率が非常に悪く、食事で摂取した量のうち、20~30%しか体内に取り込まれないと言われています。
しかし、ビタミンDを一緒に摂取することでカルシウムの吸収率が高まります。
より多くのカルシウムを体内に取り入れることができるため、丈夫な骨を作る上で大きく役立ってくれるのです。
メンタルを安定させる
さらに、ビタミンDは「メンタル」にも関係していると言われています。
ココロや神経のバランスを整えてくれるのが、脳内物質の「セロトニン」。
ビタミンDはこのセロトニンの合成に関わっているため、しっかりと充足させることでメンタルが安定しやすくなると言われているのです。
実際、さまざまな研究でビタミンDの補充がうつ傾向の改善に効果があった、という報告がされています。
ビタミンDが不足するとどうなる?逆に多すぎると?

このように、さまざまな効果が期待できるビタミンD。
では、ビタミンDが不足してしまうと身体にどのような影響が起こるのでしょうか?
また逆に、過剰に摂取してしまうとどのような影響が起こるのでしょうか?
ここからはビタミンDが不足するとどうなるのか、逆に過剰摂取するとどうなるのか、ということについて解説していきます。
不足すると起こること
ビタミンDが不足すると、次のようなことが起こりやすくなります。
・感染症や病気にかかりやすくなる
前述の通り、ビタミンDは免疫を調整する役割を担っています。
不足することで免疫力が低下し、感染症などの病気にかかりやすくなってしまいます。
・骨が脆くなる
ビタミンDはカルシウムの吸収に欠かせないため、不足すると体内のカルシウム濃度が減り「低カルシウム血症」が起こることがあります。
それにより、骨が軟化してしまう「骨軟化症」、骨が曲がって成長する「くる病」、骨量がへってしまう「骨粗しょう症」などが起こりやすくなります。
・うつ症状が現れる
ビタミンDは脳内物質のセロトニンの合成に関わっているため、不足することでうつ症状などが起こることがあります。
過剰摂取すると起こること
前述の通り、ビタミンDを多く含んでいる食品は少ないため、日頃の食生活で過剰症になることはまずありません。
しかし、サプリメントを摂取している場合は、規定量を越えて摂取しすぎると過剰症が起こることがあるため注意が必要です。
・高カルシウム血症
ビタミンDの過剰症でもっとも気を付けるべきなのが「高カルシウム血症」。
ビタミンDにはカルシウムの吸収を高める効果があるため、過剰に摂取するとカルシウムの吸収量も必要以上に増えてしまい、血液中のカルシウム濃度が高すぎる状態になってしまうのです。
そうなると、のどの渇き・倦怠感・多尿から始まり、重症化すると幻覚・錯乱・昏睡を伴う脳の機能障害を引き起こすことがあります。
最悪の場合、死に至ることもあるため過剰な摂取は気を付けなくてはいけません。
日本で売られているサプリメントを用量・用法を守って摂取する分には、過剰摂取になる可能性は低いため過度に心配する必要はありません。
ビタミンDを充足させる方法

さて、ビタミンDについて基礎知識が得られたところで、ここからは「どうすればビタミンDを充足させることができるか」ということについて解説していきたいと思います。
ビタミンDが豊富な食品を食べる
前述の通り、ビタミンDを多く含む食品というものはあまり多くありません。
しかし、全くないというわけではありません。
一部の食品にはたくさんのビタミンDが含まれており、そういった食品を積極的に食べることでビタミンDを摂取することができます。
おすすめのビタミンD食材は、以下の通りです。
・鮭
鮭には、1切れ(100g)あたり32μgビタミンDが含有されています。
1切れ食べるだけで、成人の推奨量である8.5μgを十分に賄うことができます。
・しらす干し
しらす干しには、100gあたり61μgものビタミンDが含有されています。
14g(大さじ3杯程度)で、8.5μgのビタミンDを摂取することができます。
・干しきくらげ
干しきくらげには、100gあたり85μgものビタミンDが含有されています。
10g(6枚程度)で、8.5μgのビタミンDを摂取することができます。
この他、カレイ、サンマ、イワシといった食品にもビタミンDが豊富に含まれています。
手のひら日光浴をする
最も効率よくビタミンDを補給することができる方法が「日光浴」。
とはいえ、やはり美容のことを考えると紫外線をガンガンに浴びるのは避けたいですよね。
そこでおすすめなのが「手のひら日光浴」。
手のひらは他の身体の部位と比べてメラニン色素が少ない部位で、日焼けの心配が少ないと言われています。
手のひらだけ日焼け止めを塗っていない状態で、夏なら5分程度、冬なら30分程度、手のひらを太陽の光に当ててみましょう。
これだけでもかなりビタミンDを合成することができますよ。
ビタミンD強化食品を利用する
最近は、ビタミンDを強化した食品というのもたくさん販売されています。
たとえば、
・ビタミンD強化卵
・ビタミンD強化ウエハース菓子
・ビタミンD強化牛乳
などはスーパーなどでもよく見かけます。
こういった食品を取り入れることで、ビタミンDを補給することができます。
潔くサプリメントを利用する
食事や日光浴でビタミンDを摂取するのは難しい、という方は、潔くサプリメントを活用してしまうというのもひとつの方法!
ビタミンDのサプリメントは比較的安価な価格で販売されていることも多いので、ぜひ取り入れてみましょう。
国内製のサプリメントなら、基本的に用法・用量を守って摂取すれば過剰症はあまり心配する必要はありません。
(ただし、海外製のサプリメントの中にはビタミンDの含有量が非常に高いものもあるので必要です。)
一日あたりのビタミンD摂取量の耐容上限量は、成人で100μg(4000IU)と設定されているので、その量を超えないように気を付けましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本日は、免疫のビタミンと言われる「ビタミンD」について解説いたしました。
現代人は深刻なビタミンD不足に陥っていると言われています。
他の栄養素とは異なり、普通の食事をしているだけではビタミンDは不足してしまいがちなので、積極的に摂るよう心掛けてみてくださいね。