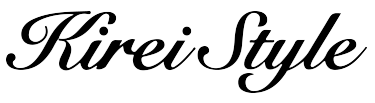「最近、肌がくすんで見える」
「ハリがなくなってきた気がする」
それ、もしかすると“糖化”のサインかもしれません。
年齢とともに深まるシワやたるみ、くすみといったエイジングサイン。
その裏に潜む見えない敵“糖化”は、肌や体の老化を進める大きな要因として、いま美容や健康の世界で注目を集めています。
そんな糖化を効果的に防いでくれると言われている食品があります。
それが、さまざまな“ハーブ”や“スパイス”。
日頃からハーブやスパイスを摂取することで、糖化を防ぎ、若々しさを保つことができる可能性があるということで、近年研究が盛んに進められているんです!
本日は、そんな糖化を防ぐことができるハーブに着目。
ハーブやスパイスの力が糖化にどう働きかけるのか?気になるメカニズムからおすすめハーブ、今日から始められるケアのヒントまでをたっぷりお届けします。
「糖化」は、体の中で起こる“焦げつき現象”

近年少しずつ耳にするようになった“糖化”というワード。
美容雑誌やSNSでよく聞くけど「イマイチよく分からない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここで今一度、糖化についておさらいしてみましょう!
糖化とは、体内の余分な糖とたんぱく質が結びついて、AGEs(Advanced Glycation End Products/終末糖化産物)という老化物質が生成される反応のこと。
この反応は、科学的には“焦げ”と同じ現象であると考えられています。
パンケーキを焼くと、いい香りと共にだんだんと生地が茶色くなり“焼き目”や“焦げ”ができていきますよね。
これも実は、卵に含まれる“たんぱく質”と小麦粉やお砂糖の“糖”が結びつき、糖化することで、このような現象が起こるのです。
つまり「焦げる」とは「糖化する」ということなのです。
パンケーキの中で糖化が起こる分には、ただ焼き目ができて美味しくなるだけなので問題ないのですが、これと同じ現象が人間の体内でも起こることがあります。
日頃からご飯などの炭水化物やお砂糖たっぷりのスイーツをたくさん摂取していたり、インスリン(血糖値を下げるホルモン)のはたらきが悪かったりすると、使いきれなかった糖が血中に余ってしまいます。
すると、余った糖は体内のたんぱく質(コラーゲンや赤血球など)と結びつき、“糖化”を起こします。
そして糖化がどんどん進んでいくと、最終的に“AGEs(エージーイーズ/ 最終糖化産物)”という物質が生み出されるのです。
このAGEsがなかなかの厄介者。
コラーゲンやエラスチンといった美肌成分にダメージを与え、肌のハリや透明感を失わせてしまいます。
それだけではありません。
AGEsは肌の老化だけでなく、血管の硬化、骨密度の低下、内臓機能の衰えなど、全身の加齢症状にも関与していることがわかってきました。
しかも、いったん体内に蓄積されたAGEsは自然に排出されにくく、なんと年齢とともに加速度的に増えていくと言われているんです。
困ったものですよね…。
知らぬ間に糖化が進む生活習慣とは

糖化の大きな原因は、食後の血糖値の急上昇により血中に糖が有り余ってしまうこと。
高GI食品(白米やパン、菓子類など)を食べたとき、血中の糖が一気に増加すると、過剰な糖が体内のたんぱく質と結びついてAGEsが作られてしまいます。
また、以下のような生活習慣も糖化を進めるリスクとなります。
運動不足:筋肉量が減ると血糖をうまく消費できず、高血糖状態に。
睡眠不足:糖代謝に関わるホルモンの分泌が乱れる。
ストレス過多:ストレスホルモン「コルチゾール」が血糖値を上げやすくする。
過度な紫外線:活性酸素の発生によってAGEsの蓄積を促進。
つまり、日常のちょっとした行動が、肌や体を“糖化させる生活”につながっているかもしれないのです。
ハーブとスパイスが糖化にアプローチする3つのメカニズム

糖化を防ぐためには、まずは基本の「食事」「運動」「睡眠」を整え、ストレスや紫外線を避ける生活を心がけることが大切。
ですが、“ハーブ”や“スパイス”の力を借りると、より効果的に糖化のケアを行うことができます。
では、ハーブが糖化に対してどう働きかけるのでしょうか。
近年の研究では、以下の3つのメカニズムでハーブが抗糖化に役立つことが報告されています。
1. 抗酸化作用によるAGEs生成の抑制
美容に詳しい方なら「酸化」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これは、身体の“錆び”に喩えられるもので、糖化と並んで美容の大敵ということで知られていますよね。
実は、「糖化」と「酸化」はお互いに深く関与しあっていて、酸化ストレスがAGEsの生成を促進すると言われています。
多くのハーブはポリフェノールやフラボノイドなどの抗酸化成分を含んでおり、これを摂取することで酸化ストレスを軽減し、結果的にAGEsの形成を抑制することができます。
・ローズマリー
カルノソール、カルノシン酸、ロズマリン酸といったさまざまな抗酸化成分を含んでいます。
・セージ
ローズマリーと同様に、カルノソール、カルノシン酸、ロズマリン酸といったさまざまな抗酸化成分を含んでいます。
・シナモン
主要な香り成分であるシンナミックアルデヒドには抗酸化・抗炎症作用があります。その他、プロアントシアニジン、クマリンといった抗酸化成分も含んでいます。
2. 糖とタンパク質の結合を直接阻害
糖化反応の初期段階では、糖と体内のタンパク質が結合し、「アマドリ化合物(Amadori products)」という中間体を経てAGEs(最終糖化産物)へと進行します。
一部のハーブは、この初期の糖化反応を直接阻害する成分が含まれており、AGEsの初期段階での生成を防ぐ効果があります。
・ターメリック
カレーなどに使われることの多いターメリックには「クルクミン」という成分が含まれており、これが糖とタンパク質の結合を直接阻害すると言われています。
・玉ねぎ
私たちにとって身近な野菜である玉ねぎは、スパイスとして使用されることも。
そんな玉ねぎには、糖とタンパク質の結合を直接阻害する「ケルセチン」という成分が多く含まれています。
・ローズマリー
ローズマリーに含まれるカルノソール、カルノシン酸、ロズマリン酸といった成分は、抗酸化作用だけでなく糖化の初期段階を阻害する効果もあります。
3. 糖の吸収抑制による血糖値の安定化
前述の通り、糖化は高血糖状態(血中に糖が有り余っている状態)で促進されやすくなります。
つまり、高血糖な状態をできる限り防ぐことで、糖化も予防することができるのです。
ハーブの中には、消化酵素の働きを抑えたり、糖の吸収を遅らせたりすることで、血糖値の急上昇(血糖スパイク)を防ぐものがあります。
これにより、糖化のリスクを間接的に低下させることができます。
・フェヌグリーク
スパイスの一種であるフェヌグリークには、ガラクトマンナンという成分が含まれており、糖の吸収をゆるやかにすることで食後の高血糖を防いでくれます。
・ギムネマ
ギムネマはサプリメントとして使用されることも多いハーブ。
ギムネマ酸という成分が、小腸で糖の吸収を抑え、インスリンの分泌を調整することで食後の急激な血糖値上昇を抑えてくれます。
・シナモン
シナモンに含まれるプロアントシアジニンは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌を促し、効力を高める作用があると言われています。
4. AGEsの分解促進や排出サポート
AGEsは一度できてしまうとなかなか排出されにくいと言われていますが、最近の研究では、一部の植物由来成分が体内に蓄積したAGEsの分解や排出を促進する可能性も示されています。
これはまだ研究段階ですが、肝機能や腎機能をサポートするハーブの使用が間接的にAGEs排出に貢献することが考えられています。
・ターメリニック
ターメリックには胆汁の分泌を促進し、肝臓のデトックス機能を高める働きがあります。
これにより、AGEsやそれに伴う代謝老廃物の排出をサポートしてくれる効果があると考えられています。
・ダンデライオン(西洋たんぽぽ)
ダンデライオンにも胆汁分泌を促進する働きがあると言われています。
肝臓の浄化作用を高めることで、AGEsの処理を効率化します。
ハーブ&スパイスで始める“ゆる糖化ケア”

このように、一部のハーブやスパイスを上手に取り入れることで、糖化を防ぐことができることがお分かりになったかと思います。
とはいえ問題なのは「どのように生活に取り入れるか」ということ。
中には私たち日本人の食生活にはなじみのないハーブやスパイスもあるため、どのように取り入れていけばいいのか迷ってしまいますよね。
ですが、ハーブやスパイスを普段の生活に取り入れるのは意外と簡単!
次のような方法で積極的に抗糖化ハーブ&スパイスを取り入れてみましょう♡
1. ハーブティーを飲む
ハーブの抗糖化作用にあやかる最も簡単な方法は「ハーブティーを飲む」ということ。
ローズマリーやセージ等はハーブティーに使われることの多いハーブなので、市販でもこれらを使ったお茶の商品が多く販売されています。
ハーブの香りで心もすっきりとするので、リラックスタイムにもおすすめです。
2. スパイスカレーを作る
ターメリック、玉ねぎ、フェヌグリークといった抗糖化スパイスをまとめて摂取することができるのが「カレー」!
カレーはさまざまなスパイスをブレンドしたものなので、今日ご紹介したスパイスはもちろんのこと、それ以外の健康にいいスパイスも摂取することができるのでとてもオススメ。
市販のカレールーはカロリーや糖質の摂りすぎになってしまう可能性もあるため、ぜひ「カレー粉」を使ってスパイスカレーを作ってみてください。
自分で好みのスパイスをブレンドしてみるのも良いかもしれません。
3. チャイを飲む
もうひとつスパイスを摂るのにおすすめの方法が「チャイ」を飲むということ。
チャイはシナモンをはじめとするスパイスでできているので、デザート感覚で飲めるのにしっかり抗糖化作用を期待することができるのです。
とはいえ、レストランなどで提供されるチャイにはお砂糖がたくさん使われていることも多いため、自宅でお砂糖控えめで作るか、お砂糖の代わりにオリゴ糖を使って作るのがおすすめ。
奥深い香りと優しい甘さのチャイは、一度飲むと病みつきになってしまいますよ。
このように、スパイスやハーブはちょっとした工夫で取り入れることができるので、ぜひ挑戦してみてくださいね。
まとめ
糖化は、年齢とともに誰にでも起こる自然なプロセス。
でも、植物の力を借りてやさしく整えることで、そのスピードをゆるやかにし、自分らしい“美しい年齢の重ね方”を実現することができます。
ハーブは、体と心にそっと寄り添ってくれる頼もしい存在。
美しさだけでなく、日々の暮らしに癒しとバランスを与えてくれるパートナーとして、これからのエイジングケアにぜひ取り入れてみてください。
「糖化に負けない、私になる。」
その一歩を、ハーブと一緒に踏み出してみませんか?