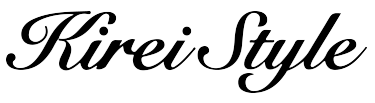つい気になってしまう、デリケートゾーンの臭いのお悩み。
他の人たちがどうやって対処しているか気になるけど、内容が内容だけに相談しづらいですよね。
実は、デリケートゾーンの臭いには種類があります。
自分の臭いがどのタイプかを把握し、正しくケアをして対処する必要があります。
「アソコの臭いが気になって、突然のセックスが心配・・・」
「彼にクサいって思われたらどうしよう…。」
そんな風にお悩みの方も、適切な対策を取ることで解消することができます。
本日は、デリケートゾーンの臭いの種類・原因と対処法、さらに急なセックス前に臭いを消して”いい匂い”に変える方法もご紹介します。
INDEX
百年の恋も冷める?!アソコの臭いに対する男性のホンネ
多少ニオっているとは分かっていながらも、
「みんな同じだし大丈夫でしょ。」
「男性はそこまで気にしてないはず。」
なーんてたかをくくっているそこの女子!あまいあまい!
実は、男性の多くは女性の臭いを気にしているのをご存知でしたか?
20代~30代の男性を対象に「女性のデリケートゾーンの臭いが気になったことがありますか?」というアンケート*を取ったところ、なんと3人に1人(34.9%)の男性が『はい』と回答。
さらに「デリケートゾーンの臭いと恋愛は関係ありますか?」という質問に対しては、40.9%もの男性が『はい』と回答しました。
つまり、アソコの臭いによって「百年の恋が冷める」可能性も大いにあるというわけなんです。
これはかなりショッキングな結果ですよね・・・。
*調査概要
・調査名:女性のデリケートゾーンに関するアンケート
・調査日:2019年6月18日(火)~2019年6月24日(月)
・調査方法:インターネット調査
・調査人数:1,045人
・調査対象:全国20代~30代の男女
・モニター提供元:ゼネラルリサーチ
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000043815.html
デリケートゾーンの臭いと種類と原因
デリケートゾーンは、きちんとケアをしないと臭いが発生しやすい部位ナンバーワン。
でも、大好きなあの人にこんな臭いを嗅がれて幻滅されてしまうなんて、絶対にイヤですよね。
では、どうしてこんなにも臭いが発生しやすいのでしょうか?
デリケートゾーンの臭いにはさまざまな原因が複合的に絡んでいて、その原因によって臭いも異なります。
まずは、自分の臭いがどのタイプなのか特定してみましょう。
アソコの臭いの種類と原因(1)酸味のある臭い
デリケートゾーンから「酸味のある臭い」「酸っぱい臭い」がするという場合、
基本的には正常な状態だと考えられます。
というのも、デリケートゾーンはもともと酸性のため、ほんの少し酸っぱいような臭いがするのが普通だからです。
とはいえ、耐えがたいようなすっぱい臭いはまた別の要因が隠れている可能性もあるため、
婦人科や性病科を受診した方が良いかもしれません。
アソコの臭いの種類と原因(2)魚臭い
デリケートゾーンが「魚臭い」という場合、細菌が繁殖している可能性があります。
自分の体内にもともといる細菌や、性交渉によって相手からもらった細菌が異常に増殖している場合、
このような臭いがすることがあります。この状態を「細菌性膣炎」と呼びます。
細菌が異常増殖してしまう要因としては、
蒸れた状態が続くことや、睡眠不足・疲労・膣の洗いすぎ等によるpHバランスの乱れ、腸内環境の悪化、不衛生な性交渉などが挙げられます。
自浄作用が整ってくると自然に治ることもあります。
アソコの臭いの種類と原因(3)乳製品の臭い
デリケートゾーンから「乳製品のような臭いがする」という場合、それは健康な状態であると考えられます。
おりものの中には「乳酸桿菌(にゅうさんかんきん)」という、体に良い菌がいます。
乳酸桿菌の仕事は、乳酸を分泌すること。
この乳酸によって、膣の中が酸性(PH4.5~5.0)に保たれ、悪い菌が発生しないようにしてくれているのです。
おりものの「乳製品のような臭い」は、この乳酸によるものです。
少し独特な臭いですが、膣が健康な証なので心配する必要はありません。
アソコの臭いの種類と原因(4)酵母のような臭い
デリケートゾーンから「酵母のような臭いがする」という場合、カンジダ菌が増殖している可能性があります。
カンジダ菌自体はもともと体内に存在する常在菌ですが、
疲労やストレス、体調不良によって異常増殖するとこのような臭いがすることがあるのです。
膣やその周辺にかゆみを感じたり、
おりものがカッテージチーズ状になっているという場合、よりその疑いは高くなります。
アソコの臭いの種類と原因(5)金属のような臭い
デリケートゾーンから「金属のような臭い」がする場合、それは経血によるものだと考えられます。
生理中だけでなく、生理前や生理終了後に経血が止まってからも臭いが続くことがあります。
経血から金属のような臭いがすることは通常のことなので、心配する必要はありません。
しかし「鉄が錆びたような臭い」がする場合は経血が酸化しているサインなので、こまめにナプキンを替えるなどして清潔に保つことが大切です。
また、生理日予定日でないにもかかわらずおりものから金属のような臭いがする場合、不正出血の前兆である可能性があります。
デリケートゾーンの臭いの対策

このように、デリケートゾーンの臭いには、さまざまな原因が絡み合っています。
中には、臭いと思っていても「それが正常な状態である」ということがあるのもお分かりになったかと思います。
とはいえ、やはり自分のデリケートゾーンから臭いがしたらいい気はしないもの。
無くせるものなら余計な臭いは無くしたいですよね。
ということでここからは、臭いを消すための具体的な対策をご紹介します。
アソコの臭い対策(1)専用の石鹸を使って洗う
まずオススメなのは、デリケートゾーン専用の石鹸を使い清潔な状態を保つということです。
先ほども述べた通り、膣は絶妙なphバランス(PH4.5~5.0)によって、悪い細菌が繁殖しない仕組みになっています。
ボディソープなどによってこのphバランスが崩れてしまうと、雑菌が繁殖しやすくなり、臭いが発生してしまうんです。
デリケートゾーン専用の石鹸は、膣のphバランスを崩さないように工夫されているものがほとんどです。
ボディソープではなく、そういった洗浄料を使用することで、デリケートゾーンの状態を良くすることができます。
専用の石鹸を使用し、優しく丁寧に洗う習慣をつけましょう。
アソコの臭い対策(2)通気性の良い下着
通気性の悪い下着を着用していると、「高温多湿」状態になり、雑菌が繁殖しやすくなってしまいます。
コットンやシルク素材などの通気性の良いショーツを着用することで、ムレを防いで雑菌が繁殖しづらくなります。
最近はデザイン性も高く、通気性も良い下着がたくさん販売されているので、好みのものを探してみるのもおすすめです。
また、生理中はこまめにナプキンを交換することで、雑菌の繁殖や経血の酸化を防ぐことができます。
アソコの臭い対策(3)良質な睡眠と適切な食生活
免疫力の低下は、膣の状態とダイレクトに影響します。
特に疲れている方やストレスが溜まっている方は、免疫力が下がりやすいので注意が必要。
まず心がけるべきは、良質な睡眠。
忙しい現代人にとっては中々難しいことかもしれませんが、最低でも6時間、できれば7~8時間の睡眠を取るよう心がけましょう。
また、腸内環境の悪化が臭いの原因になってしまう可能性もあるので、腸内環境を整えることも大切。
乳酸菌・ビフィズス菌を多く含む食品や水溶性食物繊維を積極的に摂るようにしましょう。
一方、カンジダ症の場合はカンジダのエサとなる糖質を控えたり、
パン・ビールなどの酵母を多く含む食品はできるだけ避けるようにしてください。
急なセックス前にアソコをいい匂いにする方法は?
このように、デリケートゾーンの臭いを改善するためには日ごろからの心がけが重要ですが、
どんなに清潔に保っていたとしても、やはり日中は多かれ少なかれ臭いが発生してしまうもの。
「今すぐ!速攻で臭いを消したい!」というタイミングもありますよね。
そんなときは、デリケートゾーン用の消臭スプレーを使用するのがおすすめです。
消臭スプレーというと「脇用」「足用」などはよく見かけますが、「デリケートゾーン用」というのはなかなか見かけませんよね?
そこで今回は、急なセックスにも対応できる、おすすめのデリケートゾーン用消臭スプレーをご紹介したいと思います。
臭いを”いい匂い”に変える?!『ハーバルラクーンナチュラルミスト』

それがこちら!
株式会社ビズキが販売する「ハーバルラクーンナチュラルミスト」です。
ハーバルラクーンナチュラルミストは、数少ない貴重な「デリケートゾーン用の消臭ミスト」のひとつ。
この可愛らしいミストが、いざというときの消臭ケアにとっても重宝するんです♡
では、その理由をご説明したいと思います。
ハーバルラクーンのメリット(1)消臭力が高い
先ほども述べた通り、デリケートゾーンは様々な要因により、臭いがとても強くなりやすい部位です。
生半可な消臭ケアでは、その強い臭いを消しきることは難しいと言えます。
特に、セックスなどのアソコの臭いがバレやすいシチュエーションでは、根本から臭いを消し去る必要がありますよね。
そこで活躍するのが、ハーバルラクーンナチュラルミスト。
ハーバルラクーンに配合されている消臭成分は「IPMP(イロプロピルメチルフェノール)」と呼ばれるもの。
さまざまな種類の臭いを消臭する効果に優れていて、その消臭効果はなんと「約89~99%」!!
また、効果の持続時間も長いので、デート前に1回スプレーしておくだけでも、24時間消臭効果を得られることが期待できます。
ハーバルラクーンのメリット(2)肌へのやさしさを考えた処方

とはいえ、「そんなに消臭効果が強いと、負担になるんじゃ・・・?」と心配になってしまいますよね。
先ほども述べた通り、デリケートゾーンはとても敏感なので、
ちょっとしたphバランスの崩れが、悪臭を強めてしまう原因にもなります。
しかし、ハーバルラクーンナチュラルミストに配合されているIPMPは刺激が少ない成分なので、
デリケートゾーンにも安心して使うことができます。
また、膣のphを考えた処方になっているため、
phバランスを崩してしまうことなく消臭することが可能です。
美肌成分も配合されているため、デリケートゾーンのお肌を整える効果が期待できるのも嬉しいポイント♡
ハーバルラクーンのメリット(3)携帯できる
ハーバルラクーンナチュラルミストの大きなメリットが「持ち運びができる」ということです。
手の中にすっぽりと納まるコンパクトなサイズなので、いざという時でもこっそりとお手洗いに持っていくことができます。
また、万が一見られてしまっても、可愛らしいデザインで化粧水にしか見えないので、恥ずかしくありません。
しっかりと臭いを取り除きたい時は、トイレットペーパーに多めにスプレーしてデリケートゾーンをふき取ると、
まるでシャワーを浴びたかのようにすっきりします♡
かさばらないので、バッグやポーチに忍ばせておくにもとっても便利。
「いつ緊急事態になっても大丈夫!」という安心感があります。
ハーバルラクーンのメリット(4)お風呂上がりのような香り
ハーバルラクーンは、ただアソコの臭いを消臭してくれるだけではありません。
シュッとするだけで、まるでお風呂あがりのようないい香りに変えてくれるんです♡
ハーバルラクーンに採用されているのは、
清潔感溢れる「サボン・ド・スイート」の香り。
男性ウケの良い石鹸系の香りで、ひと吹きするだけで清楚な可愛らしさを演出。
香り方もとってもさりげなくて上品です。
ただ臭いを消してくれるだけでなく”いい匂い”にしてくれるというのは嬉しいポイントですよね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本日は、「デリケートゾーンの臭い」についてお話ししました。
アソコの臭いが気になっていると、
彼とのセックスも心から楽しむことができませんよね。
日ごろからのケアと、いざという時の消臭ケアで、
24時間ニオわない私を目指しましょう。
ハーバルラクーンナチュラルミストの詳細はこちらからご覧ください♡
<参考URL>
・BIZKI.STORE https://bizki.jp/
・サラサーティー https://www.kobayashi.co.jp/brand/sarasaty/orimono/
・ソフィ https://www.sofy.jp/ja/advice/period-changes/34.html
・ラブコスメ https://www.lovecosmetic.jp/category/jamu/special/nioi_i.html
記事監修者プロフィール
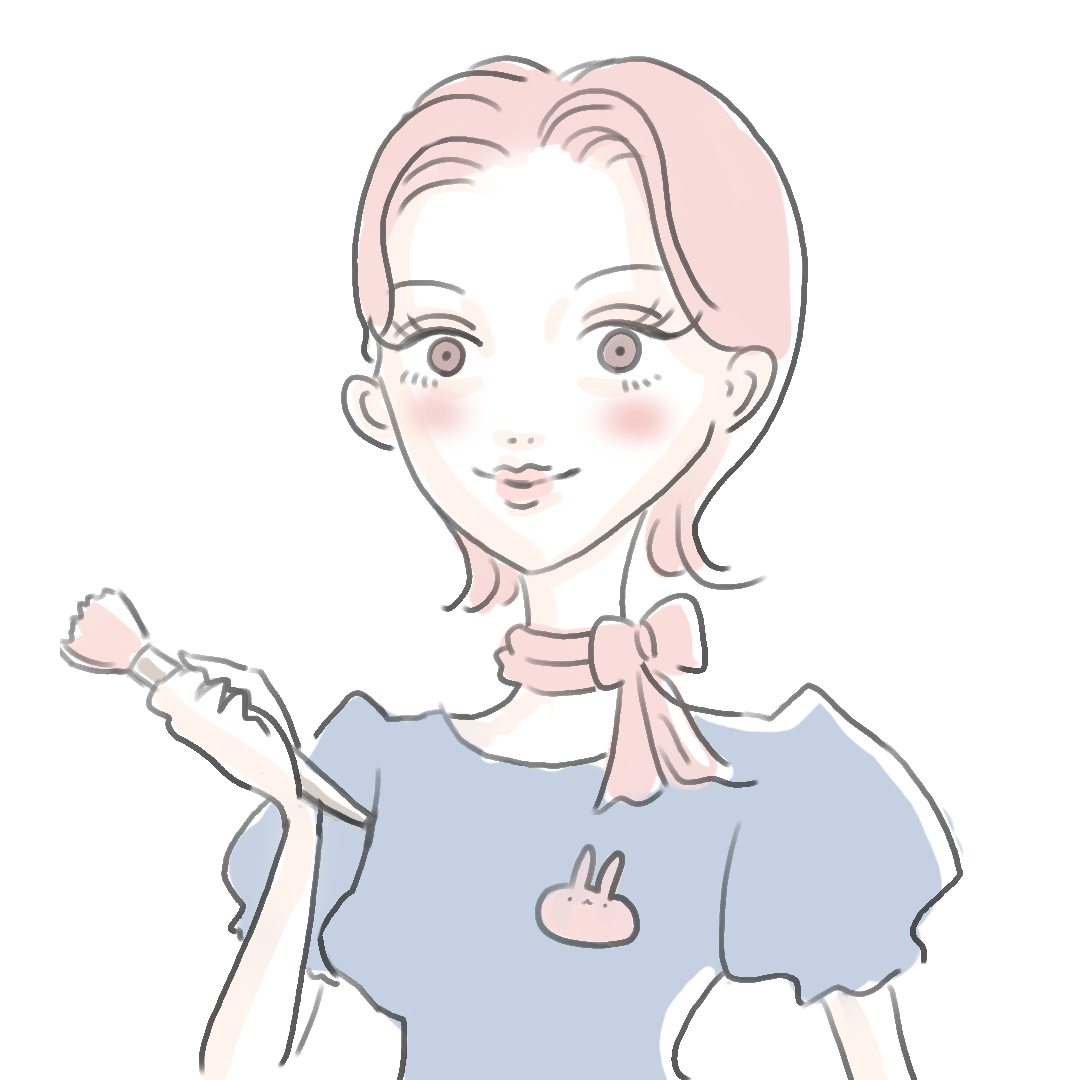
コスメコンシェルジュ
宇佐美うさ(うさみ・うさ)
東京都下生まれのコスメコンシェルジュ。
美容業界に従事し約10年。化粧品販売員・化粧品商品開発者・美容ライター等の経歴を持つ。
近道でキレイになるための方法や、化粧品成分の読み解き方を発信すべく活動している。
一番の関心事はエイジングケア。
保持資格
化粧品検定1級
掲載日:2024.04.01